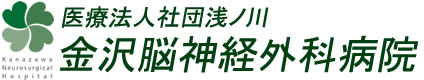医療安全管理のための基本的考え方
医療安全は、医療の質に関わる重要な課題であります。また、安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、当院の職員個人が、医療安全の必要性・重要性を施設及び自分自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り、安全な医療の遂行を徹底することがもっとも重要であります。このため、当院では、本指針を活用して、当院に医療安全管理委員会(以下、「委員会」といいます。)及び医療安全管理室(以下、「管理室」といいます。)を設置して医療安全管理体制を確立し、委員会の協議のもとに、独自の医療安全管理規程及び医療安全管理のためのマニュアル(以下「マニュアル」といいます。)を作成いたします。また、インシデント報告(ヒヤリ・ハット事例)及び医療事故の評価分析によりマニュアル等の定期的な見直し等を行い、医療安全管理の強化充実を図る必要があります。
個人情報保護法に基づく基本的な考え方
「個人情報保護方針」に基づく本院が取り扱う個人情報の適切な保護についてその是非を委員会で審議し、職員に通知しています。
医療安全の組織
医療安全推進担当者会(安全管理室)
目的:ヒヤリ・ハットレポートを収集し,その原因を調査、分析、対策等を立案します。 「誰が」ではなく「何が」原因かを調査分析、対策を考え委員会に提案しています。 委員長:診療統括部長 委員:安全推進担当者(安全管理室メンバー) 開催:週に1回の定例会を開催しています。
医療安全管理委員会
目的:医療安全推進担当者会議からの提案や報告したことについて討議します。 委員長:診療統括部長 委員(各部のリスク・マネージャーを兼ねる):病院長、副院長、医師、事務長、看護部長、副看護部長、看護師長、検査部部長、放射線部部長、リハビリテーション部部長、薬剤部部長、管理課長、栄養部部長、看護部主任 開催:月1回の定例会を開催しています。緊急時は、委員長或いは院長が招集しています。
事故調査委員会
目的:医療事故の原因調査を行い、再発防止のための予防策を立てます。必要に応じて、当該部門の責任者を通じて教育・指導を行います。 委員長:病院長 委員:事務部長、看護部長、診療統括部長、医療安全推進担当者 開催:病院長が召集します。
院内ラウンドを定期的に行っています。
医療安全管理室室長・副室長、医療安全推進者で毎月、ラウンドチェック表を用いて院内ラウンドを行い、後日指摘事項を各フロアーに書類で知らせています。
目的
- 医療安全に関わるルールの認識度と実践状況を確認する
- 5Sの確認する
- 職員とのコミュニケーションを図りながら現場の問題点を見いだし安全予防対策の実施につなげる。
患者相談窓口
- 患者等からの苦情や相談に応じられる体制を確保するために、施設内(総合受付)に案内板を設置し患者相談窓口を常設しています。
- 患者相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者及びその責任者、対応時間等について、マニュァルに明示しています。
- 相談により、患者や家族等が不利益を受けないよう適切な配慮を行っています。
- 苦情や相談で医療安全に関わるものについては、医療安全管理室に報告し、安全対策の見直し等に活用しています。
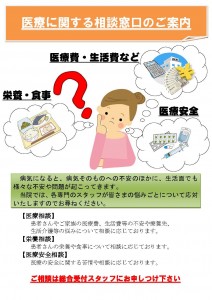
医療安全管理及び個人情報保護法のための職員研修を行っています。
個々の職員の安全及び個人情報保護法に対する意識、また安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上等を図るため、医療に係る安全管理及び個人情報保護法の基本的考え方及び具体的方策について、職員に対し以下のとおり研修を行っています。